『「フウケイ」展にむけて』増田玲(東京国立近代美術館 主任研究員)
「フウケイ」と題された写真展。それぞれ四人の写真家の作品によって構成された、二つの連続する展示において、鑑賞者は、「フウケイ」をめぐる一見ばらばらな作品群に出会うだろう。ここでの「フウケイ」とは、もはやこれまで「風景」という言葉で了解されていたさまざまな枠組みを無条件に前提とはしていない、あるいはできないという認識に立ったそれぞれの写真家が、カメラ/写真を媒介に外界と向かい合い、それぞれのやり方で立ち上がらせた、何らかの外界の「見え」であり、外界と内面が接する界面に結ばれたイメージのことだ、と、とりあえず定義しておこう。
その「フウケイ」をめぐる写真家たちのとりくみの成果は、二つの会期のそれぞれにおいてある方向性をもって呈示される。その違いはかならずしも明確ではなく、したがって今回の展覧会は、鑑賞者にとって、それぞれの写真家の作品とともに、それらが集合的に提起している問題の在り処を、各々考える機会でもある。ここでは試みに、第一の会期(DIVISION-1)では外界に、第二の会期(DIVISION-2)では内面に、少しずつその重心が寄っているととらえてみたい。




まずは外界よりに重心を置いたDIVISION-1から、畔柳寿宏と相馬泰による都市写真の呈示するフウケイについて考えてみよう。一定の方法論を採用する彼らの作品は、もともとは外界に対する分析的なまなざしを契機としているように思われる。しかし畔柳の作品は、その分析の報告ではなく、むしろ分析のプロセス自体を空間に上書きしてしまったような奇妙な余剰をはらんだフウケイを出現させる。それは実は、イメージを分割してプリンターによって出力する際の、イメージと用紙のタテヨコ比の関係で生じた余剰部分にすぎないのだが、その余剰をはらんだフウケイに、私たちは時間や記憶や予兆といったものを勝手に読み込み、上書きし始める。対照的に、相馬の提出する抑制の効いたフウケイは、都市写真のある種の類型をあえて踏襲している。中判フィルムのシャープな描写力による、情報量の多い、しかしながら地名やランドマークなど固有名を持った場所へと結びつく手がかりは周到に除外された街角のイメージ。ふつうならそこには「場の無意識」といったものを読み取りたくなるところだが、余剰をはらんだ畔柳のフウケイと併置されるとき、相馬のそれはもはや分析的であるというより、フィクショナルな性質を帯びつつあるように見えてくる。情報のネットワークに覆われた日常を生きる私たちの今日的リアリティに見合うのは、分析の対象というより、そこに過剰な意味を上書きしていくような外界との接し方かもしれないからだ。
外界に軸足を置いて生み出されるフウケイが、かならずしも分析や読解の対象とならないという意味では、山方伸の今回の試みはより徹底している。その場の光に反応すること、という条件のみを自らに課し、撮影された写真群は、場所も時期も対象との距離もさまざまで、被写体自体はきちんと写っているから一見すると身辺雑記風なのだが、たとえばそれらを「日常」といった言葉に回収するのでなく、その表面にとどまって見ることを私たちは求められている。写真家はただひたすら写真を通じて「ほら、それ」と指差すだけである。「それ」として示されている対象(=被写体)も、示そうとしている主体(=まなざしの起点としての写真家)もここではあまり問題ではなく、いわば文脈を欠いてなお指示代名詞としての機能する写真のふるまいだけが、イメージの数だけ宙づりにされ、その都度の光への反応として乱反射している。中村綾緒が、カメラ/写真を媒介にとらえる外界もまた、分析や読解の対象といった姿勢とはまったく様相を異にしている。それらはつねに不確かで、生成しあるいは消滅するような変化のただ中にある。夜の公園に集まる人々であったり、あるいは水とたわむれる身体の様相であったりと、中村が外界の不確かなありさまをとらえる際のモティーフはさまざまだが、それらは山方のスナップショットがそうであるように、被写体それ自体は大きな意味を担ってはいない。そうではなく、不確かな世界を「ほら、それ」と指示することのできるカメラ/写真のふるまいに力点が置かれている。ここでのフウケイは、もっぱらそうしたカメラ/写真のふるまいによって成立しているのである。そのようにふるまうカメラ/写真とは、写真家にとってもうひとつの他者=外界でもある。


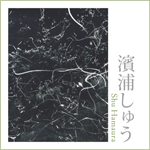

次にDIVISION-2で展示される作品を考えていこう。ここではフウケイを成り立たせる契機は、より内面のほうに置かれているように見える。
坂本政十賜と田中マサシが呈示するのは、ともに植物をめぐる「フウケイ」だ。坂本の作品では主として孤立した植物、田中の作品では群れとしての植物という違いはあるが、ともに私たちをとりまく日常的な光景のなかに、ふだんはあまり気に留められることもなく存在しているような植物が、ここでのフウケイを成立させるための契機となっている。外界からある要素をとりだし、それに注目する。しかもそれらをイメージとして定着させる仕方は、いずれも写真のもつ描写性をストレートに活用したものだ。とすれば、彼らのフウケイは外界の側に軸足を置き、それを記録し、分析や読解する行為のように見える。しかしそうではない。それらの植物は、何らかの意図をもってそこに植えられているという意味で人為であり、それ自身のサイクルに従って成長しているという意味で自然である。植物は私たちに対して無関心な、絶対的な他者でもあり、同時に生命的な存在として私たちに親和的でもある。ここでは植物それ自体よりも、そうした植物の両義的な存在の仕方が重要なのだ。植物を契機として成立している彼らのフウケイには、外界に関する報告であると同時に、それを見る私たちの内面がひきだされる場でもあるという両義的な様相が現れる。より風通しのよい坂本のフウケイと、より濃密で陰影をはらんだ田中のそれとは、異なる種類の反応を、見るものからひきだすだろう。
濱浦しゅうと横澤進一の呈示するフウケイは、それぞれのイメージがとらえられた「とき」と「場所」とにより強く結びついているように思われる。そしてそのフウケイの成立の仕方は対照的だ。濱浦の場合は、その「とき」、外界と交錯することによって生じた内面からの反応が、その都度、結節点として、閉じられた小宇宙のような濃密な場=フウケイを成り立たせる。それが成立するには、その「とき」でなければならなかったし、そしてその「とき」でなければならない理由は、おそらく多分に撮り手の内面の側にある。他方、横澤の場合は、その「場所」のみが生じさせる反応として、フウケイが成立している。横澤はいつもある同じ東京郊外の土地をフィールドとしている。そしてその「場所(=外界)」からの刺戟によって内面の反応が生じ、それに促されるようにして進められる持続的な横澤の歩行の軌跡として、連鎖的なフウケイが産み出されていく。濱浦のそれがその「とき」を契機とする凝縮や凍結のようなものであるとすれば、横澤のそれはその「場所」を契機とする増殖や沸騰のようなものだ。
「フウケイ」と題された写真展にむけての、このみじかい考察において示した枠組みは、あくまで暫定的なものだ。そしてそれぞれの写真家の作品もまた、「フウケイ」にたいするとりくみの現在地の報告であり、それらが一時的に構成する「フウケイ」展のあとに、またそれぞれ新たな方向へとそれぞれのとりくみが進められていくだろう。今回の展覧会は、鑑賞者にとって、それぞれの写真家の作品とともに、それらが集合的に提起している問題の在り処を、各々考える機会でもある。その思考は、展覧会場を出たときに、鑑賞者たちの外界へのまなざしにいかなる変化をもたらすのだろうか。
増田玲(東京国立近代美術館 主任研究員)
